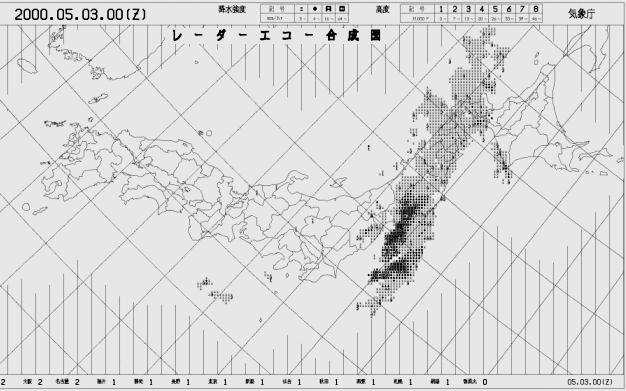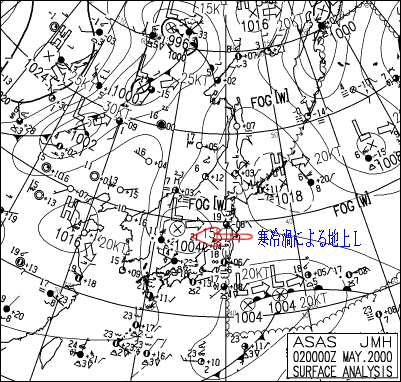 日本海にある1004hPaの低気圧が寒冷渦に伴う低気圧です。
日本海にある1004hPaの低気圧が寒冷渦に伴う低気圧です。この地上天気図だけを見ていると「な〜んだ、大したことないよ。」と思われるような低気圧ですね。
「寒冷渦(cold vortex)とは?」にも書いておきましたが、寒冷渦の低気圧性循環は対流圏上層ほど顕著で、地上では明瞭に認められないこともあり地上天気図において低気圧と解析されない場合もあるようです。
寒冷低気圧(コ−ルド・ロウ)或いは切離低気圧(カットオフ・ロウ)とも言われる。中心部の温度が周囲より低い温帯低気圧のことである。北半球では風は低気圧の中心のまわりを反時計回りに回転している。 その低気圧性循環は対流圏上層ほど顕著で、地上では明瞭に認められない事もある。渦の中心を通る鉛直断面で見ると圏界面が大きく垂れ下がっていてそのくびれた部分では周囲より温度が高い。ここに密度が小さい空気があるので、対流圏上層や中層では周囲より気温が低いにもかかわらず周囲より低圧となっている。寒冷渦が形成されるまでの時間的経過は、1.対流圏上層に発達中の気圧の谷があり、その背後(西側)には寒気が入り込んでいる。2.気圧の谷の振幅が大きくなって 3.ついに南の端が切り離された形となり、等温線も閉じた形となり寒冷渦となる。
寒冷渦に覆われると大気の成層は不安定となり、寒冷渦に伴って上昇流があるので雷雨が発生しやすい。また、冬季の寒冷渦は日本海側に豪雪をもたらすことがある。
(気象科学事典より)
寒冷渦の一般的な特徴を挙げてみます。
1.2000年5月2日の実況
地上実況天気図(5月2日9時)
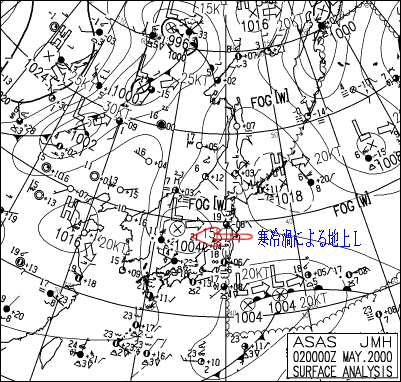 日本海にある1004hPaの低気圧が寒冷渦に伴う低気圧です。
日本海にある1004hPaの低気圧が寒冷渦に伴う低気圧です。
この地上天気図だけを見ていると「な〜んだ、大したことないよ。」と思われるような低気圧ですね。
「寒冷渦(cold vortex)とは?」にも書いておきましたが、寒冷渦の低気圧性循環は対流圏上層ほど顕著で、地上では明瞭に認められないこともあり地上天気図において低気圧と解析されない場合もあるようです。
ひまわり赤外画像(5月2日9時)
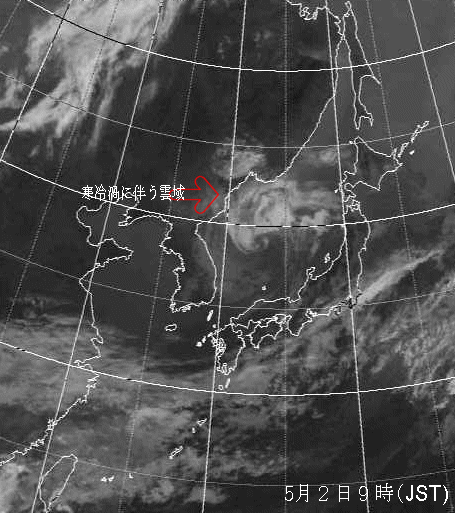 地上実況図と同じ時刻のひまわり赤外画像です。日本海に渦を巻いたように見える雲域が寒冷渦に伴うものです。
地上実況図と同じ時刻のひまわり赤外画像です。日本海に渦を巻いたように見える雲域が寒冷渦に伴うものです。
また、日本列島の南岸に沿うように高層雲が見えますがこれはジェット気流によるものでしょう。
500hPa高層実況図(5月2日9時)
500hPa面の高層実況図です。日本海には閉じた等高度線とその中にLがあり、これが寒冷渦です。
日本列島南岸沿いにはサブジェットが、バイカル湖付近にはポ−ラ−ジェットが流れ寒冷渦はこの間に位置しています。また、日本列島付近は南西風の場となり南からの暖気が入りやすくなっています。
さらに、この時期としては強い寒気(-24℃)を伴って大気成層は非常に不安定となっています。
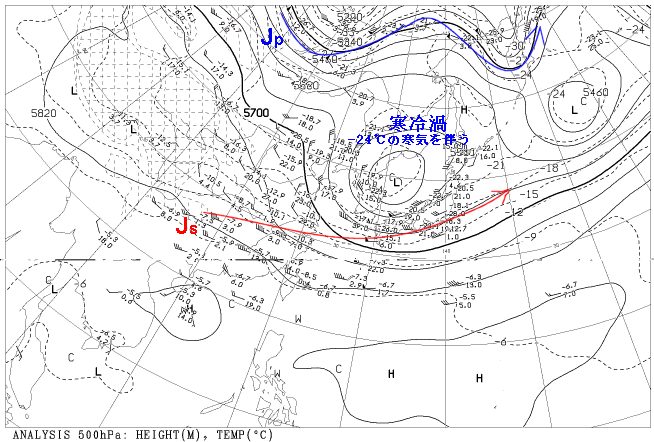
2.2000年5月3日の予想図
つぎに、5月2日9時(日本時)初期値の予想図を見てみます。
これらの予想図を見ていく上でのポイント。
| 500hPa高度・渦度(左上) | 500hPa気温・700hPa湿数(右上) |
| 地上気圧・12〜24時間降水量・風向風速(左下) | 850hPa気温・風向風速 700hPa上昇流(右下) |
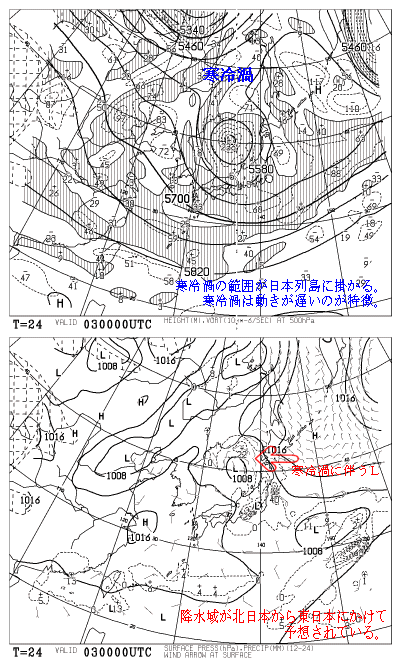 | 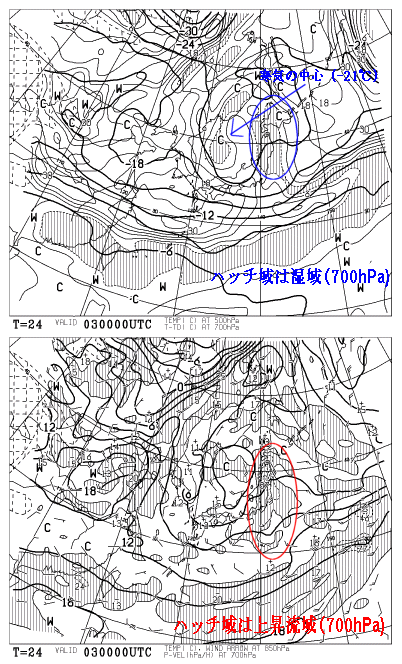 |
850hPa相当温位予想図 (5月2日9時初期値 T=24)
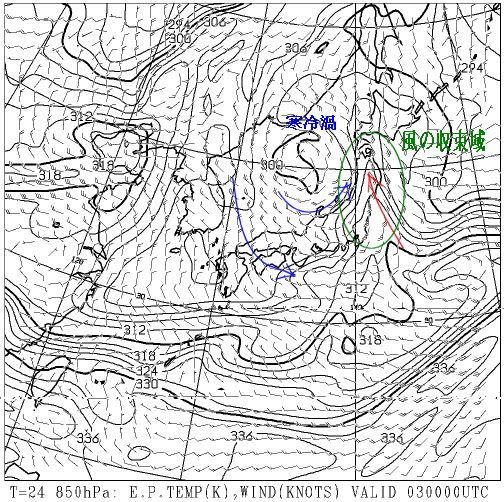 日本海には風の低気圧性循環が見られ、上空の寒冷渦に対応しています。
日本海には風の低気圧性循環が見られ、上空の寒冷渦に対応しています。
東北地方では等相当温位線が楔状に北に向かって入り込み、且つ、この地域では寒冷渦の周りを回る南西〜南南西風と南東〜南南東風が収束しています。下層での風の収束は上昇流を強化します。
3.5月3日9時の実況
下の図は5月3日9時現在のレ−ダ−エコ−合成図です、この図のエコ−域と上の相当温位予想図における風の収束域を見比べてみますと良い対応を見せています。これは寒冷渦の東から南東側にあたっています。